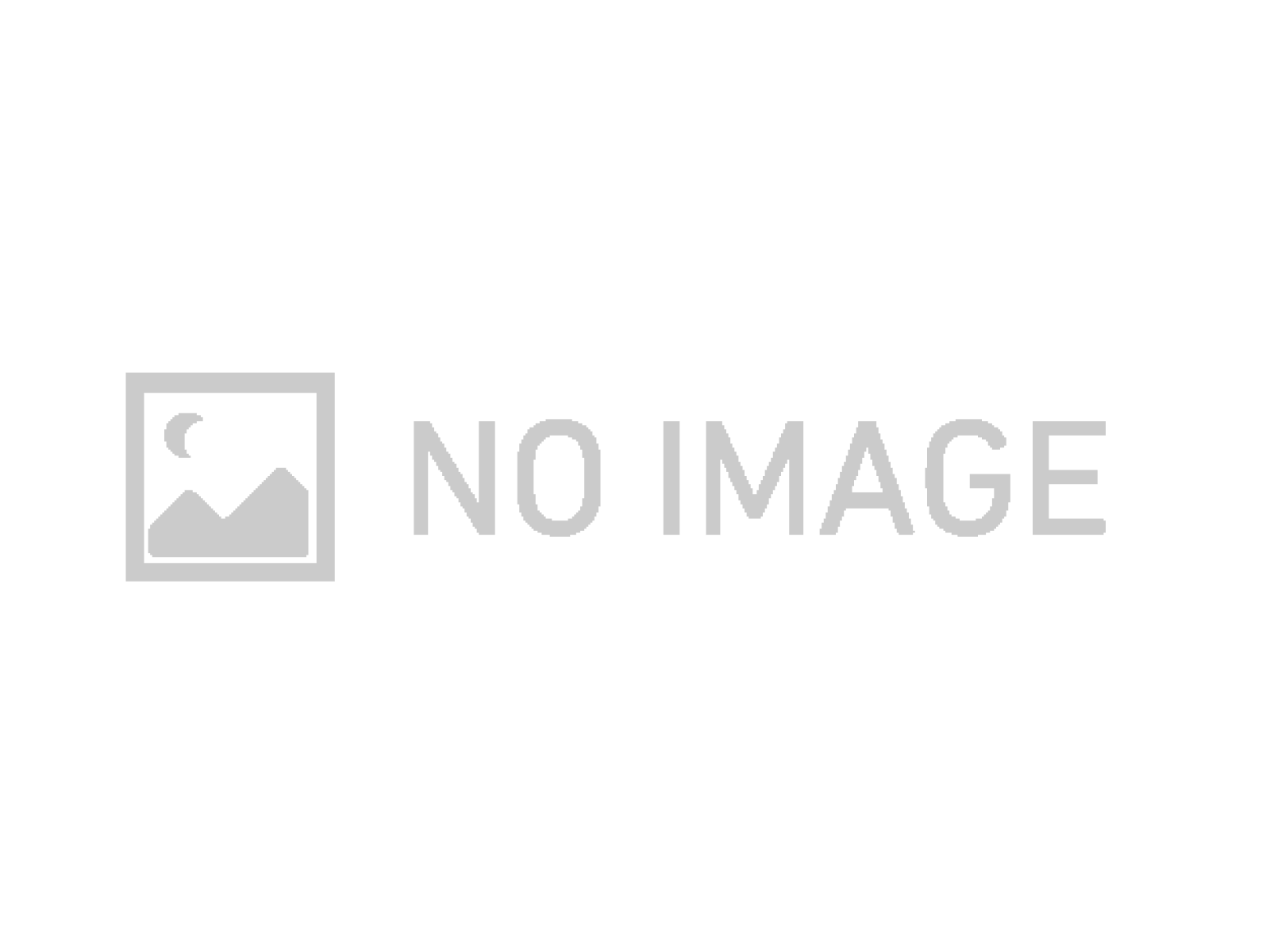2021月3月24日㈬の午前9時から午前11時の間、当館ホームページの2021年4月~2022年3月のスケジュールの入力作業を行います。
当館のホームページのシステム上、アクセスの遮断ができないため、入力作業中に上記の期間の予定を当館ホームページのスケジュールで確認されますと、誤った情報が表示されてしまいますので、2021月3月24日㈬の午前9時から午前11時の間は、当館ホームページのスケジュールを確認されないようお願いいたします。
※入力作業が終了次第、こちらのブログと当館Twitterにてご連絡いたします。
→2021/03/24㈬ AM11:00 入力は終了いたしました。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。